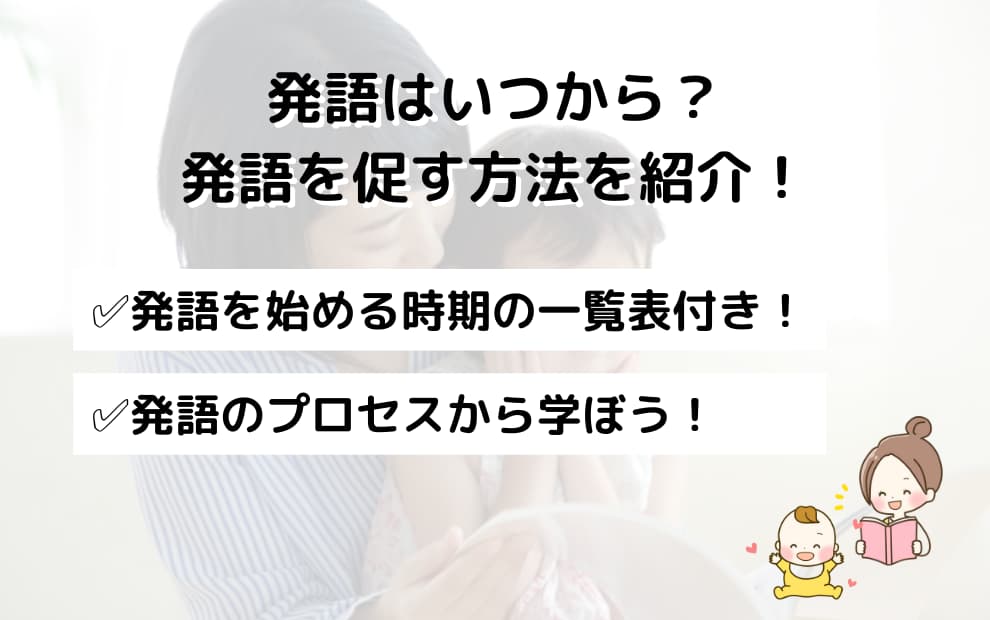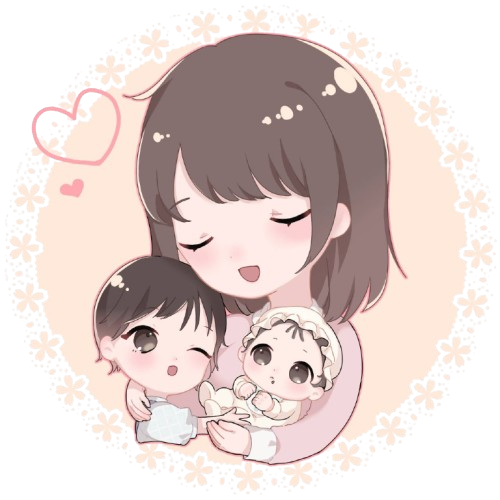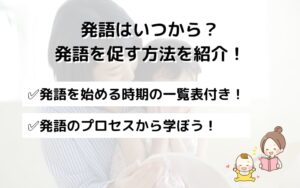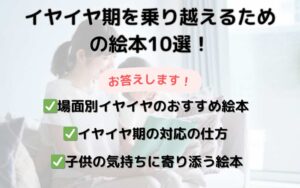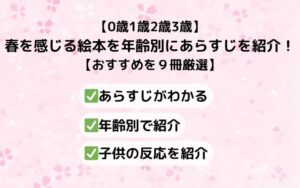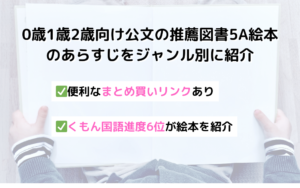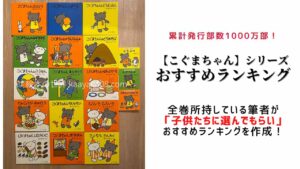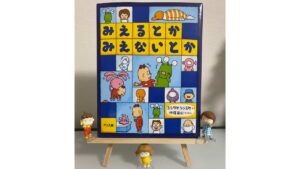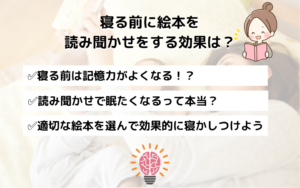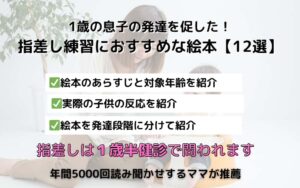発語は、国の調査によると
1歳で約5割、1歳6か月で9割以上の子に見られます。
そう聞くと、
「周りの子が喋り始めたのに、うちの子はまだ…」
そんな不安を感じてしまいよね。
 かや
かや心配ですよね。息子も2歳の時発語は5語ほどでした。
遅れている理由が、どこにあるのか一緒に考えてみましょう。
本記事では、発語の平均時期と遅れて見える理由、さらに“発語を引き出す3つの方法”を発達心理の視点から解説します。
この記事を書くにあたって参考にした資料・文献
本記事では、以下の文献を参考にしています。
*直接的に要約しているものではありません。
どれも有名なもので、ネットで検索すると見る事ができるので、心配な方は一読ください。
Christakis, D. A., & Zimmerman, F. J. (2009).
国際医学世界的標準誌掲載
Young children and screen time (TV, videos, and computers): Implications for language development. Pediatrics, 128(5).
→ 画面視聴が長いほど、親子の会話が減り、語彙の伸びがゆるやかになる傾向を指摘。
Madigan, S. et al. (2019).
医学界・統計エビデンスによる研究
Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. JAMA Pediatrics, 173(3).
→ 幼児期のスクリーン時間が長いほど、2年後の言語発達スコアが低い傾向。
Kuhl, P. K. (2007).
国際的基盤理論を築いた方の研究
Is speech learning ‘gated’ by the social brain? Developmental Science, 10(1).
→ 言語学習は「社会的なやり取り(対話)」を通じてのみ成立することを実験的に示した研究。
✔この記事を書いた人
✅子供のくもん:全国英語6位国語3位
✅漢検協会賞受賞。
年間5000回の読み聞かせ経験から「リアルに役立つ情報」をお届けします。
【発達心理学×実体験レビュー】
発語はいつから?【国のデータで確認】
まずは、6か月から1歳6か月までの赤ちゃんの発語割合を見てみましょう。
以下は、厚生労働省「乳幼児身体発育調査報告書(平成22年・平成12年)」をもとにした発語開始時期の比較表です。
| 平成 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳 | 1歳1か月 | 1歳2か月 | 1歳3か月 | 1歳4か月 | 1歳5か月 | 1歳6か月 |
| 22年 | 0% | 1% | 4% | 9% | 18% | 35% | 50% | 65% | 76% | 82% | 87% | 90% | 93% |
| 12年 | 0% | 0% | 4% | 10% | 20% | 40% | 62% | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% | 95% |
表からもわかるように、
8か月頃から発語が見られ始め、1歳でおよそ半数、1歳6か月では9割以上の子どもが「ママ」「ワンワン」などの意味ある言葉を話し始めています。
一方で、平成12年と平成22年を比べると、1歳での発語率が62%→50%へとやや低下しています。
昔より発語時期が後ずれする理由
【 発達心理から見る仮説】
発語開始時期が昔より少し遅くなった背景には、“対人関係の体験の質”の変化が関与している可能性があります。特に以下の3要素が、最新研究で指摘されています。
共同注意:言語発達の予測因子
共同注意とは、「親と子どもが同じ対象を見て、その対象について一緒に意識を向ける行為」です。
このスキルは1歳前後で急速に発達し、子どもの語彙発展と強く関連しているという縦断研究もあります。



昔は家庭内での対話や共有体験が自然に多く、共同注意を育みやすい環境だった可能性があります。
模倣とジェスチャー:言語獲得の先駆運動
関わりの質:双方向性が鍵
ただ見ているだけ・受動的な体験では言葉は定着しにくく、むしろ親子の応答性・やり取りのテンポが発語促進に効果的とされます。



現代は画面視聴や受動的体験が増えがちで、その分、こうした“やり取り時間”が減っていることが、発語開始がやや後ろにずれた一因かもしれません。
発語は「脳の成熟」だけでなく、社会的なやり取りの“回数と質”によって決まると考えられています。
そのため、核家族化が進み、テレビやYouTubeといった受動的な情報体験が増えたことが、
平均的な発語のタイミングに影響していると考えられています。
つまり、昔よりも「人と関わる機会」や「やり取りの時間」が少なくなったことで、
発語までの準備(まねる・指差す・共有する)に必要な経験が減りやすい環境になっているのです。



でも、うちはテレビも見せすぎてないし、よく話しかけています。



もちろんです。
ここでお話しているのは、“多くの家庭の平均的な傾向”として見られる統計的な変化です。
ひとりひとりの子どもに焦点を当てて、“なぜうちの子の発語が遅いように見えるのか”を少しずつ深堀って確認しましょう。
発語が遅くても焦らなくていい理由
発語が遅くても、以下の 3つのポイント が見られていれば、
そこまで心配する必要はありません。
ただし、不安があるときはいつでも専門機関に相談してOKです。
親子が安心して過ごせることが一番です。
ポイント①「言葉を“理解”している」
発語よりも先に育つのが、「理解(受容言語)」です。
たとえ言葉が出ていなくても、次のような反応があるなら大丈夫です。
- 名前を呼ぶと振り向く
- 「ちょうだい」「バイバイ」などの言葉に反応する
- 絵本で好きなページを覚えて笑う



これは脳の中で言葉の意味を理解する回路が育っているサインです。
心理学的には、理解がある子は「発語の準備段階」に入っており、
時間の経過とともに自然と表出(話す)へ進んでいきます。
言葉の理解が難しいという人には言葉の理解を促すオノマトペ絵本がおすすめです。
→発語を促す絵本
ポイント②「まね・指差し・やり取りがある」
発語の基盤になるのは、「社会的なやり取り」です。
言葉を覚える前に、人との関係を通して学ぶ力が育っていれば安心です。
- 指差しで伝えようとする
- 親の動作をまねする
- アイコンタクトや笑い返しがある



これらはすべて、社会的コミュニケーション能力の発達サインです。
最近の研究では、こうした「やり取りの回数」が多いほど、
脳の言語野(ブローカ野・ウェルニッケ野)が発達しやすいことがわかっています。
指差しがまだな人は指差しに必要な共同注意を育てる絵本がおすすめです。
→指差しを促す絵本
ポイント③「安心して沈黙できている」
意外かもしれませんが、安心して沈黙できる環境も言葉を育てます。
子どもは「話しても大丈夫」と感じたとき、初めて自分から言葉を出します。
- 叱られずに受け止めてもらえる
- 親の表情が穏やか
- 無理に「言ってごらん」と促されない



こうした安心感は、脳の発話中枢(ブローカ野)を活性化させると報告されています。
焦って言葉を引き出すより、親が「待つ」姿勢を見せることが、
子どもにとって最大の“言葉の安全基地”になります。
安心できるからこそ、次のステップにいけるんですね。
🩺心配なときは「相談=予防」
もし以下のような様子がある場合は、一度専門機関に相談してみてください。
- 呼んでも反応が少ない
- 指差しやまねっこが見られない
- 表情の変化が少ない
相談は「異常を見つけるため」ではなく、
「その子に合った関わり方を知るため」のサポートです。
早期支援は将来の発達を助けるポジティブな選択です。
発語を促す3つの方法
発語は、ただ「話しかける」だけでは育ちません。
子どもが「伝えたい!」と思える瞬間を、親子のやり取りの中で増やしていくことが大切です。
発達心理学の観点から見ると、発語を促すには以下の 3つのステップ が重要です。
①「共同注意」を育てる
子どもが何かを指差したり、親と同じものを見て笑ったりする行動を、
「共同注意」 と呼びます。
これは発語の“スタート地点”です。
- 子どもが指差したものに「○○だね」と応える
- 絵本を一緒に見て「ワンワンいたね!」と共感する
- 親が驚いた表情や笑顔を見せて、感情を共有する
こうしたやり取りを繰り返すことで、
子どもは「見て・感じて・名前を聞く」サイクルを学びます。



共同注意は、発達心理学で「言語獲得の最初の社会的スキル」とされていて、共同注意を育てるには絵本が最適です。
②「まね・模倣」を促す
発語の前段階では、「まねっこ」 がとても重要です。
これは脳の「ミラーニューロン」が活性化する行動で、
見たこと・聞いたことを自分の中で再現する練習になります。
- 「バイバイ」などの身ぶり遊びを一緒にする
- オノマトペ(わんわん、ぽっとん)を使ってリズムで伝える
- 子どもが声を出したら「まねして返す」
これを繰り返すことで、子どもは「自分も発していい」という体験を積み、
言葉の模倣へと自然につながっていきます。



ミラーニューロン研究では、
模倣行動が運動野・言語野の連携を強めることが確認されています。
③「ポジティブな感情」を共有する
子どもは、楽しいとき・うれしいときにもっと話したくなります。
発語を促す最大のエネルギーは、ポジティブな感情の共有です。
- 「できたね!」と一緒に喜ぶ
- 絵本を読んで笑い合う
- 発音したときにオーバーリアクションで褒める
これにより、脳の報酬系(ドーパミン回路)が働き、
「話す=楽しい」と学習していきます。



肯定的な情動を多く見せる親ほど、子どもの情動調整・発語が進むと報告されています。
情動調整に最適な絵本はノンタンシリーズです。
2歳ごろの気持ちをそのままに書き出す絵本は、感情のラベリングができ、情動調節に最適です。
発語を促す絵本の選び方(年齢別&タイプ別)
「どんな絵本を選べば、ことばの力が育つの?」
そう感じたら、発達心理の視点で見てみましょう。
絵本には「感覚」「まね」「感情」を刺激する要素があり、
それぞれの発達段階に合った本を選ぶことで、発語を自然に促すことができます。
①【0歳〜1歳前半】感覚を刺激する絵本
この時期はまだ「ことばを理解する前」の段階。
大切なのは、音とリズムで耳と脳を育てることです。
- オノマトペ(擬音語・擬態語)が多い絵本
- シンプルでコントラストの強いイラスト
- ページごとのテンポが一定
💡おすすめテーマ:
「じゃあじゃあびりびり」「もこもこもこ」など
→ 音と視覚が一致する体験が、“聞く楽しさ”を育てます。



聴覚刺激は、言語野の前段階である「音韻処理ネットワーク」を活性化させることがわかっています
②【1歳前後】まねと指差しを引き出す絵本
この頃は、共同注意(いっしょに見る・指す)が盛んになる時期。
絵本を通して、親子で「同じものを共有する体験」を増やしましょう。
- 身近な名詞や動作が1ページ1つ
- 指差ししやすい構図
- 「なにかな?」「どれかな?」と声かけしやすい内容
💡おすすめテーマ:
「おべんとうバス」「ぴょーん」など
→ 「見て→指して→まねる」の循環が、発語を引き出します。



共同注意は、言語理解と社会性の両方を支える発達の核心とされています。
指差しは発語への第一歩!
→指差しを促す絵本
③【1歳半〜2歳】感情を共有できる絵本
発語の数が増えるのは、感情がことばと結びついたときです。
この時期の子は「言いたい気持ち」が育ちはじめます。
- 主人公の表情が豊か
- ストーリーに共感しやすい
- 親子で笑ったり驚いたりできる内容
💡おすすめテーマ:
「しろくまちゃんのほっとけーき」「ノンタン」など
→ 喜怒哀楽を“声に出して表す”練習になります。



感情共有を通した発話体験は、ドーパミンの働きを強め、
「話す=楽しい」という感覚を脳が学習します。
ノンタンやこぐまちゃん絵本が気になる方は
→ノンタン絵本比較で選べる一覧表
→こぐまちゃん絵本比較で選べる一覧表
発語を促す絵本おすすめリスト
ここでは、実際に発語を促す効果が高い絵本を、年齢別に紹介します。
すべて「発達心理の理論」「実体験」の2つを根拠に選んでいます。
発語を引き出すコツは、年齢と発達段階に合った“ことばの心地よさ” を選ぶこと。
  |   |   | |
| 本のタイトル | じゃあじゃあ びりびり | おべんとうバス | ノンタン ぶらんこのせて |
| 対象年齢 | 6か月ごろから | 1歳ごろから | 2歳ごろから |
| 特徴 | オノマトペと「物の名前」をセットで覚えられる単語理解に優れた絵本 | 「〇〇君?」「はーい」 コール&レスポンス絵本で模倣やコミュ力が育つ! | お友達との関わり方や言葉をノンタンに共感しながら学ぶ絵本 |
| amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
もっと絵本を知りたいかたは
→発語を促す絵本0歳1歳2歳向け
よくある質問(FAQ)
- 発語が遅いと発達障害の可能性がありますか?
-
🧠発語が遅い=発達障害、とは限りません。
発達心理学では「発語が遅い子=言語理解が遅い子」ではなく、理解は進んでいても表出が遅れるタイプも多いことがわかっています。
一方で、次のような特徴がある場合は早めに相談しておくと安心です。・呼んでも振り向かない
・指差しや視線の共有が少ない
・模倣や「バイバイ」などの身ぶりが見られないこれらは「社会的やり取り」よりも“ことば”が遅れているタイプのサインかもしれません。
早期相談は「異常の発見」ではなく、「子どもに合う関わり方を早く知る」ためのものです。 - テレビやYouTubeを見せると発語が遅れますか?
-
見せ方によります。
研究では、受け身での長時間視聴は発語の遅れにつながる傾向がある一方、
親子で会話しながら一緒に見る(共同視聴)場合は、言語発達を助けることがわかっています。Madigan et al. (2019, JAMA Pediatrics)
→ 2歳未満で1日2時間以上の受け身視聴は、発語の遅れリスクを2.7倍に。
以下のポイントに注意しながら見る事を推奨します。
💡ポイント
・見終わったあとに“実際の体験”につなげる
・一緒に見て「これなあに?」「おんなじだね」と話しかける - どこに相談すればいいですか?
-
不安を感じたときは、早めの相談=安心の確認です。
相談先は以下の通りです。
・保健センター(1歳半・3歳健診など)
・小児科・耳鼻科
・児童発達支援センター・療育センター - 発語が進む家庭で共通していることは?
-
最新研究では、共通点は「回数」ではなく「会話の質」です。
Gilkerson et al. (2017, JAMA Pediatrics) は、
「親子の会話ターン(交互発話)」が多い家庭ほど、
子どもの語彙力が高いことを報告しています。共通している習慣は以下の通りです。
・否定せず「もう一回言ってみよう」で応援する
・子どもの反応を“待つ”
・子の発音をまねして返す
・伝えたがりを受け止める
まとめ|発語は「理解→やり取り→表出」の流れで育つ
発語は“急に話し出す”ものではなく、
理解 → まね → やり取り → 発語 の流れの中で育ちます。
焦るよりも、毎日のやり取りの中で「伝えたい気持ち」を育てていきましょう。
✅発語の目安まとめ
| 年齢 | 発語の特徴 | 育てたい力 | おすすめの関わり方 |
| 0歳〜1歳前半 | 音・リズムを楽しむ 時期 | 聞く力・音の反応 | 擬音・リズム遊び・音のまねっこ |
| 1歳前後 | 指差し・まねで伝える時期 | 共同注意・模倣力 | 一緒に見る・ リアクション |
| 1歳半〜2歳 | 感情を言葉に変える 時期 | 表現力・社会的意図 | 絵本の感情共有・ ごっこ遊び・共感返し |
これらを意識することで、発語が早い家庭に多い”質の高いかかわり”を再現できます。
💡発達心理から見た“焦らなくていい”理由
- 言葉は「理解」から育つ(内言→外言)
- 社会的やり取り(共同注意・まね)が発語の基盤
- 安心して沈黙できる環境が「話す勇気」を生む



発語が遅くても、それは「言葉が育っていない」ではなく、
多くの場合、「言葉を出す準備をしている時間」。
絵本を通して笑い合う時間こそ、ことばのいちばん深い土台になります。
🔗発語の関連記事を読む
発達心理学×実体験で発語を促す絵本を厳選した
→発語を促す絵本16選
共同注意を育てる発語の芽となる
→指差しを促す絵本12選
0歳から2歳までの発達に合わせた絵本を厳選した
→くもんの推薦図書5A一覧表あらすじ